東洋医学とは言っても
難しく考える必要はありません。
一言で言ってしまえば
自然界の法則を
「人も同じだよね」と考え
そのまま当てはめたものです。
東洋医学では【五臓】がそれぞれ
【七情】と呼ばれる感情を
主っていると考えます。
健康な状態であれば
一時的に乱れても
自分で整える事ができますが
これが大きく乱れた時に
【心の病】として現れます。
では【心の病】が現れた時
身体にはどのような症状が出るのか
を少しだけ具体的に
いくつか例をだしてみたいと思います。
心の病(うつ病、精神疾患)
心の病や、精神疾患と聞くと
「うつ病」や「適応障害」「統合失調症」
等をイメージされるかも知れませんが
東洋医学の視点での【心の病】は
病名がつくものだけではありません。
東洋医学には
心身一如という考え方がございます。
大昔から『心と身体は一つ』として
治療をしているのです。
怒り・イライラ
イライラ・怒り
イライラする事があってイライラするのは当然です。イライラしにくい人がいるのも事実ですが、生まれ持った性格、体質が大いに影響するので、「人と比較」する必要はありません。【心の病】と捉えるのは「些細な事でイライラ」したり、「ずっとイライラ」している事です。
イライラを抑え込む
「イライラしたらダメだ」と、無理に感情を抑え込むと、やがて身体に症状として現れます。例えば「激しい頭痛」「目の奥の痛み」「ぎっくり腰」「寝違え」「回るようなめまい」等々…。関係ないように思えますが、東洋医学の視点で考えれば不自然ではありません。
イライラを爆発させる
時にはイライラが爆発してしまう事もあります。重要なのは、イライラが爆発した後にどのような感情になるのかです。いくら爆発してもすぐにイライラするのか。それとも爆発した事に対して「くよくよと落ち込んでしまうのか」では、身体の偏り方の印象が大きく違います。
思い悩む、考え続ける
一日中考え事をしている
多くの方は無自覚な事が多いです。それが当たり前のようになっているのです。何かひとつの事に取り組む時に、並行して別の事も考えている、どこか集中しきれていないような感覚の方もいらっしゃいます。何も考えずにぼーっとする事が出来ないという訴えも聞きます。
考えている事を伝えられない
考えている事をうまく言語化出来ない、もしくは伝える事が出来ない状況で溜め込み続けると身体にかかる負担は大きくなります。更に他の要因が加わる事によって「寝つきが悪くなる」「食欲減退」「お通じが乱れる」「身体が重い」「すぐに疲れる」等の症状が出ます。
当たり前に感じる
一時的な心配事が解決する事によって、症状が一気になくなる事もあります。ですが、解決できずにそのまま過ごしていると症状が徐々に強くなります。緩やかに不調が続き、気が付けばそれが「当たり前」になります。こうなると何かきっかけがない限り、気づきません。
物悲しい、やる気が出ない
やる気が出ない
身体がぐったり疲れていてやる気が出ない、これは東洋医学でいう所の『気』が不足しているような状態と考えれば当然です。ところが、いくら身体を休めても「気力が出ない」「やる気が出ない」となった時に身体に大きく偏りが出ている可能性があります。
物悲しい
理由もなく何だか「物悲しい気持ち」になりやすいタイプでもあると思います。更に大きく偏っていると、身体に出る症状としては「慢性的な鼻炎」、「肩こり」、「精神的な頻尿」、「皮膚の病(蕁麻疹・アトピー性皮膚炎等)」など、一見関係なさそうな症状も出て来る事があります。
気のせい
これらの症状は身近な人に相談しても「気のせいでしょ」とか「気にし過ぎ」と言われてしまいがちです。ニュアンスは違いますが、東洋医学の視点で考えれば十分に【気の病】です。まさに【気のせい】です。このような偏り方をしている方の多くは、スマホで身体の症状、病名等を調べて過度に落ち込み、悲しむ傾向があります。
恐れ、不安
予期不安
何か理由があって不安を抱える事は日常でもあります。このような状況も長期化すれば身体に大いに影響を与えますが、それよりも【心の病】として捉えるべきは「まだ起こるかどうかもわからない事に対しての不安・恐怖感」です。現代医学的には「予期不安」と言われます。
過度に驚く
少しの物音でビックリしてしまう。他人から見たら大げさに見える事でも、本人にとっては大きなお悩みになります。夜中に少しの物音で起きて眠りが浅い傾向も。他にも症状として「フワフワするめまい」、「耳鳴り」、「円形脱毛症」、「足先の冷え」の訴えが多いです。
鍼が怖い
これもある種「不安・恐怖」に近い感覚だと思います。過去の経験もあるかも知れません。当院では刺さらない鍼でチョンと当てるだけの治療も出来ます。これは特に精神疾患や【心の病】の方には積極的に使っています。心と身体が整って来ると鍼に対する怖さは軽減します。
これらの感情、【心の病】は
単独で出る事はまずありません。
この辺が言語化するのが難しい部分だと
患者さんの訴えを通して感じています。
是非、感じているまま相談して下さい。
一度に全て、上手に話そうとしないで大丈夫です。
治療を続けているうちに思い出す事もあります。
当院の患者さんの訴えを例としていくつかご紹介します。
※個人が特定できないよう多少脚色を加えています。
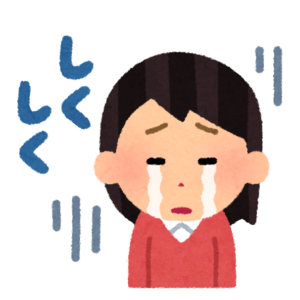
これまで毎週のようにプチ旅行を楽しんでいたが、コロナ禍を境に外出頻度が減ってから外に出るのが怖くなってしまいました。それでも週に一回家族と外食はしていたのだけど、数か月前に外食をした時に気持ちが悪くなってしまい、そこから外食も出来ていません。

昔からずっと思い悩む性格だし、それが当たり前になってます。何も考えずにぼーっと過ごす事が出来ないけど、みんなそういうものだと思っていました…。最近は仕事に対してやる気も低下気味で、人間関係でイライラする事が増えています。
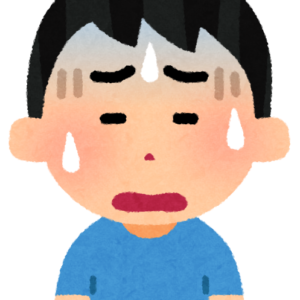
厳しいノルマのある会社に転職して、一年必死に仕事をしていましたが、一年が終わったタイミングでこれを繰り返すのかと思った途端にやる気が出なくなり、ベッドから起き上がれなくなってしまいました。心療内科に通いつつ、無理して半年程仕事を続けていたが今度は激しい回転性のめまいに襲われるようになっています。
一見複雑そうな患者さんの訴えも
東洋医学の視点で考えた時に
このように偏っているのかも知れないと
予想が出来ます。
この訴えを元にして
実際の身体の状態を確認しながら
治療を進めて行く事が出来ます。
数回の治療では、元々の体質や
現在おかれている環境の影響が強い場合もあり
すぐに好転しない事もありますが
治療を続けて行くと
段々と自然治癒力(生命力)が向上し
『心と身体』が丈夫になっていきます。
焦らず、根気強く治療を続ける必要があります。
もう一つ例を出します。
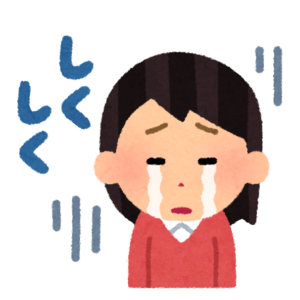
数年前にパニック障害を発症しました。電車の中で過呼吸になって以来電車に乗れなくなって、遠出が出来なくなってます。最近は徒歩での移動が多くなったせいなのか、ここ数か月で膝や足首の痛みも出ていて歩くのも大変です。運動量は減っているはずのに、食欲はやたら増えていて常に胃もたれ気味です。大人になってからは落ち着いていた蕁麻疹も、最近は頻繁に出るようになってます。
こういった症状の場合
現代医学でいうと
「心療内科」、「整形外科」
「胃腸科」、「皮膚科」
とそれぞれ通院する必要が出てきます。
必然的に薬の量も多くなります。
患者さん本人の一番の悩みは
「パニック障害」になります。
パニック障害がある事によって
様々な症状が出てきている。
それに対しても
それぞれ治療してもらいたい
という考えが一般的だと思います。
ですが
東洋医学の視点で考えた時に必要なのは
『心と身体』が
どのように偏っている事によって
症状が出ているのかという点です。
実際に『心と身体』を整えるという事は
全体に対して治療を行なうという事です。
全体の偏りを見て整えていくというのは
全部の症状が一遍に良くなる事と
一致はしません。
この方でいえば
症状が出て比較的日が浅い
「胃もたれ」や「膝、足首の痛み」は
比較的早く良くなるかも知れません。
ですが
元々若い頃に出ていた「蕁麻疹」は
体質的な部分との関係が深い事もあると
予測が立つので時間がかかるかも知れません。
パニック障害に関しても
発症してから数年が経ってます。
焦らずに治療をする必要があります。
これまでの話を踏まえて
改めて「うつ病」や「適応障害」を
どのように感じるでしょうか。
誰しもが何らかの形で
【心の病】は起こりうる事です。
逆に言えば
本人が全く自覚していないところで
それに近い状態になっている事もあります。
「心」は目に見えないものです。
陰陽で言うと『陽』の性質を持っています。
形としては捉えられないけど
確かに存在や作用は感じ取れます。
そんな複雑な心の動きを
現代医学の視点で
一定の基準で診断し、病名をつける。
非常に難しさを感じます。
例え、病院の診断で
「うつ病」や「適応障害」
とされても
東洋医学の視点で考えた時に
傾向はあっても
全く同じに偏っている事はありません。
人の心と身体は
自然と同じように
常に一定の状態ではないからです。
怒るべきところで怒れる
悲しい事があって悲しむ
それが自然です。
ところが
いつまでも同じ感情に捉われ続ける
もしくは
ある一定の感情を感じない
こうなった時が【心の病】です。
身体にも少なからず変化が出ているはずです
心と身体の変化、どちらを先に感じ取るかは
人によって違います。
ですが、この変化を感じ取れるかどうか
対処療法的に薬でその場しのぎをしたり
目を背けていると
時に大きな体の変化として現れます。
当院で行う鍼灸は、いずれもやさしいものです。
具体的に話せなくても
何か心の不調、不安定を感じているのであれば
それを訴えて下さい。
やさしい鍼でお応えします。
よくご相談頂くお悩み